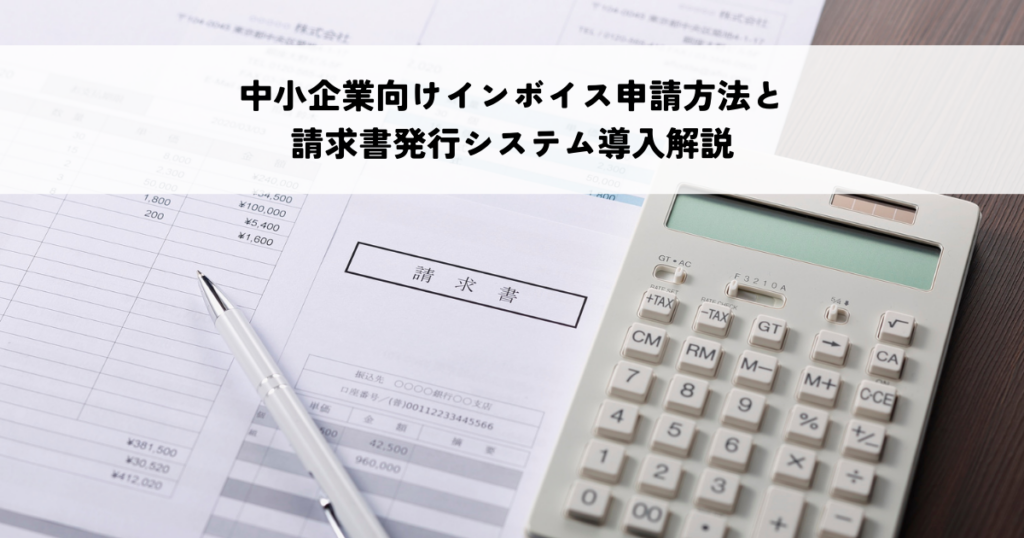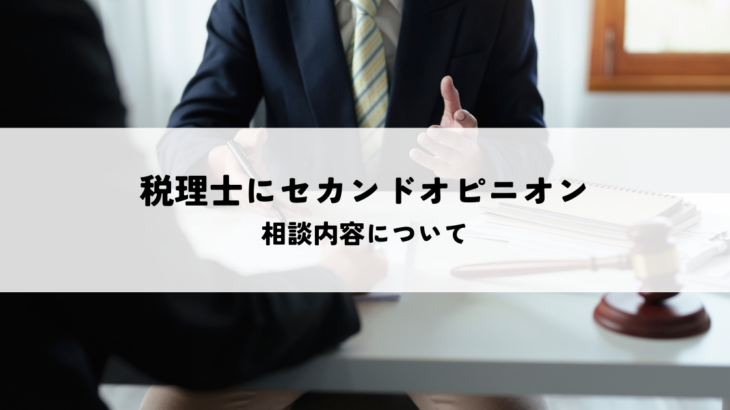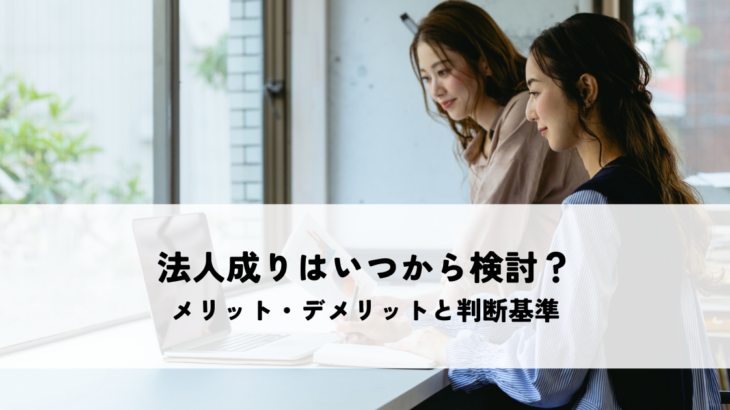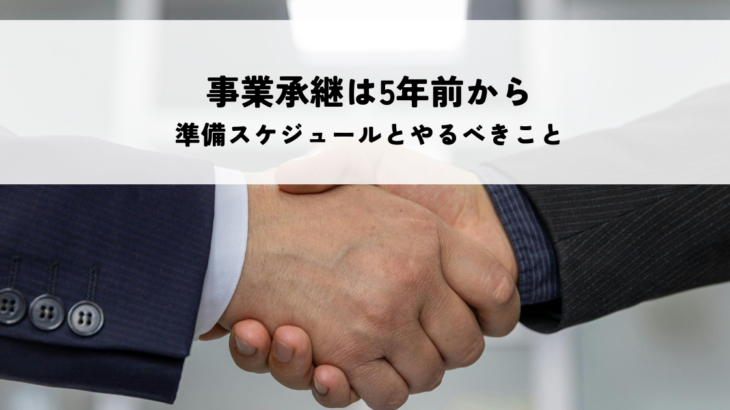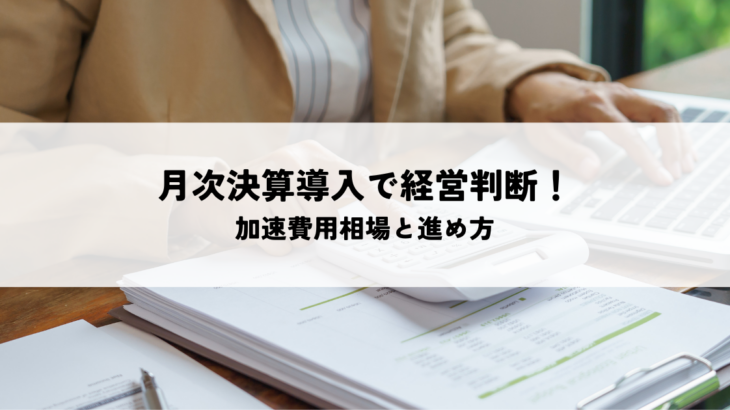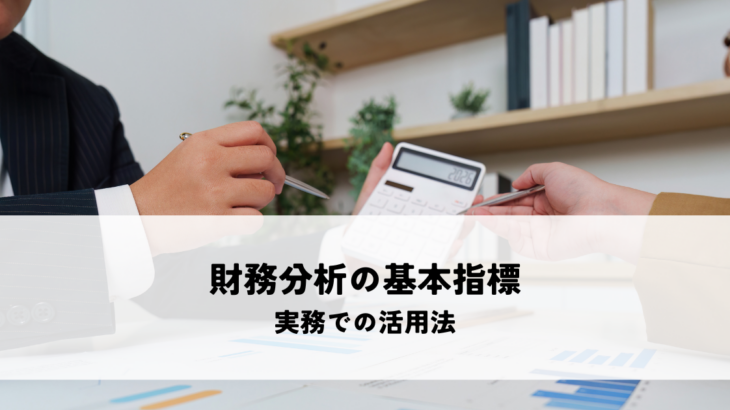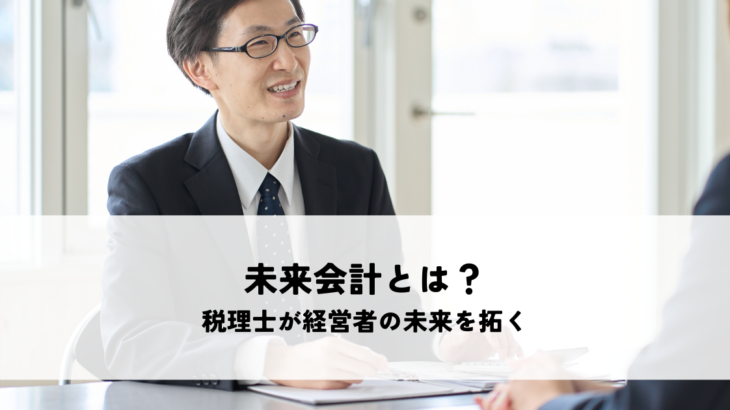2023年10月に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の仕組みを大きく変え、多くの企業にとって避けて通れない経営課題となっています。
この制度は、複数税率(標準税率10%・軽減税率8%)に対応した正確な納税額の把握を目的としていますが、特に中小企業にとっては、制度の複雑さやシステム対応にかかるコストが大きな負担となるケースも少なくありません。制度に対応しない場合、取引先から取引を見直されるリスクも考えられます。
今回は、インボイス制度への対応に必要な登録申請手続き、中小企業が押さえるべき要点、請求書発行システムの選定、そして税理士への相談方法など、中小企業がこの変化にスムーズに対応できるよう、具体的な情報を提供します。
インボイス制度への登録申請方法
e-Taxでの申請方法
インボイス制度の登録申請は、国税庁の電子申告・納税システム「e-Tax」を利用することで、オンライン上で迅速かつ簡単に完了できます。
個人事業主の場合はマイナンバーカードとICカードリーダライタ(または対応スマートフォン)、法人の場合はそれに加えてG-BizIDの利用が便利です。
e-Taxソフトやe-Taxウェブ版にログイン後、画面の指示に従って必要事項を入力し、データを送信すれば申請は完了です。
郵送に比べて登録番号の通知が早く、24時間いつでも申請できるというメリットがあります。
郵送での申請方法
郵送で申請する場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を記入し、所轄の税務署ではなく、各地域の「インボイス登録センター」宛に送付します。
申請書は国税庁のウェブサイトからダウンロードできますが、手書きでの記入ミスや書類の不足などがあると、確認作業に時間がかかり、登録番号の発行が遅れる可能性があるため、可能な限りe-Taxを利用した申請が推奨されます。
申請に必要な書類
通常、既存の事業者が登録申請を行う場合、「登録申請書」自体が必要情報のほとんどを網羅しているため、追加で法人登記簿謄本などを添付する必要は基本的にありません。
ただし、申請内容に確認が必要な点がある場合など、税務署から別途書類の提出を求められる可能性はあります。
申請前には国税庁のウェブサイトで最新の情報を確認してください。
申請期限
インボイス制度はすでに開始されているため、厳密な意味での一律の「申請期限」はありません。
登録は随時受け付けられています。
ただし、「いつから登録事業者になりたいか」によって、申請書を提出すべき時期の目安が定められています。
課税期間の初日から登録を受けたい場合は、原則としてその課税期間の開始の15日前までに申請書を提出する必要があります。
登録完了までには一定の期間を要するため、余裕を持った手続きが重要です。
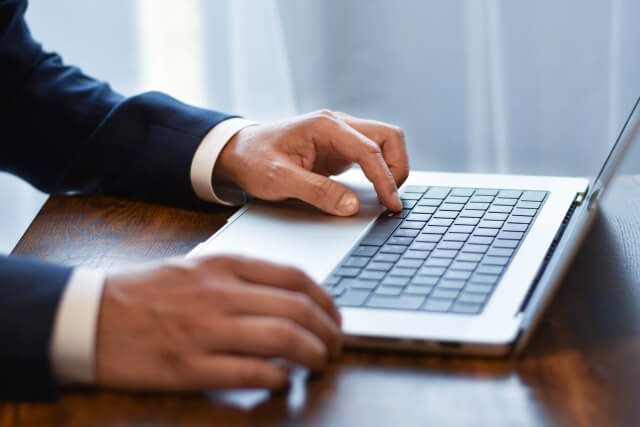
中小企業が対応すべきインボイス制度の要点は?
課税事業者と免税事業者の違い
基準期間(通常は2期前)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」となり、消費税の納税が免除されています。
インボイス制度の最大のポイントは、課税事業者である買い手が、仕入税額控除を受けるためには、原則として売り手からインボイス(適格請求書)を交付してもらう必要がある点です。
そして、このインボイスを発行できるのは、登録申請を行った「課税事業者」だけです。
そのため、免税事業者のままでは、課税事業者の取引先から値下げを要求されたり、取引を打ち切られたりするリスクがあり、売上高が1,000万円以下でもあえて課税事業者を選択(登録)するかどうかの経営判断が求められます。
インボイスの発行方法
インボイス(適格請求書)として認められるためには、従来の請求書への記載事項に加え、「登録番号」「適用税率(8%対象、10%対象の区別)」「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必須となります。
小売業、飲食店、タクシー業など不特定多数の者に対して販売等を行う事業者は、記載事項を簡略化した「簡易インボイス(適格簡易請求書)」の発行が認められています。
発行したインボイスの写しは、電子データまたは紙で7年間保存する義務があります。
仕入税額控除の注意点
仕入税額控除を受けるためには、取引先から交付されたインボイスを保存することが原則となります。
受け取った請求書がインボイスの要件(登録番号や消費税額の記載など)を満たしているか、都度確認する必要があります。
なお、制度の急激な変化を緩和するため、免税事業者からの仕入れについても、2029年9月30日までは一定割合を仕入税額控除できる経過措置が設けられています。
具体的には、2026年9月末までは仕入税額相当額の80%、その後の3年間は50%の控除が可能です。
適格請求書保存方式
インボイスは、紙媒体だけでなく電子データ(電子インボイス)で保存することも可能です。
電子データで保存する場合は、電子帳簿保存法の要件に従う必要があります。
具体的には、データの真実性を確保する措置(タイムスタンプの付与など)や、日付・金額・取引先で検索できるといった可視性を確保する措置が求められます。

インボイス制度対応の請求書発行システムの選び方
自社に合ったシステムの選定基準
請求書発行システムを選ぶ際には、自社の事業規模や取引件数、予算に加えて、「現在使用している会計ソフトと連携できるか」「電子インボイスの発行・受取に対応しているか」「電子帳簿保存法の要件を満たしているか」といった点が重要な選定基準となります。
これらの機能が揃っていると、請求書発行から経理処理、法改正への対応までを一気通貫で効率化できます。
おすすめのシステム
市場には「freee」「Money Forward クラウド」「弥生会計」など、インボイス制度と電子帳簿保存法の両方に対応した、信頼性の高いクラウド型会計・請求書発行システムが多数存在します。
多くは無料トライアル期間を設けているため、実際に操作して自社の業務フローに合うか、使いやすいかを確認してから導入を決定することをお勧めします。
導入コストの目安
クラウド型のシステムは、初期費用が無料または数万円程度で、月額利用料が数千円から1万円前後というのが中小企業向けの一般的な価格帯です。
サーバーの管理が不要で、法改正にも自動でアップデート対応してくれるため、多くの企業にとってコストパフォーマンスの高い選択肢と言えます。IT導入補助金などの対象となる場合もあります。
システム導入時の注意点
新しいシステムを導入する際には、過去の取引データの移行や、販売管理システムなど既存システムとの連携が課題となる可能性があります。
また、経理担当者だけでなく、請求書を発行する営業担当者など、関連部署の従業員への操作研修も不可欠です。
導入前に十分な計画を立て、必要であればITベンダーや専門家のサポートを受けることがスムーズな移行の鍵です。
税理士に相談するメリットと相談方法は?
税理士に相談するメリット
税理士は税務の専門家として、インボイス制度に関する的確なアドバイスを提供してくれます。
特に、免税事業者が課税事業者になるべきかどうかの判断は、取引先との関係や納税による資金繰りへの影響などをシミュレーションする必要があり、専門的な知見が不可欠です。
また、IT導入補助金などの活用支援や、将来の税務調査への対策といった面でも頼りになります。
税理士への相談方法
顧問税理士がいる場合は、まず顧問税理士に相談するのが第一です。
新たに探す場合は、税理士事務所のウェブサイトなどでインボイス制度に関する情報発信に力を入れているかなどを確認すると良いでしょう。
相談に際しては、過去の決算書や主要な取引先リスト、現在の請求書発行フローが分かる資料を準備しておくと、話がスムーズに進みます。
相談内容の例
具体的な相談内容としては、「自社は課税事業者になるべきか、その損益分岐点は?」「経過措置をどのように活用すればよいか」「取引先への価格交渉はどう進めるべきか」「自社に合った会計・請求書システムはどれか」といった、戦略的な判断に関するものが挙げられます。
費用相場
顧問契約を結んでいる場合は、月額顧問料の範囲内で相談に応じてくれることがほとんどです。
スポットで相談する場合の費用相場は、1時間あたり1万円~3万円程度が目安です。
初回相談は無料としている事務所も多いため、まずは気軽に問い合わせてみることをお勧めします。
まとめ
今回は、インボイス制度への対応について、登録申請方法からシステム選定、専門家への相談方法まで、中小企業が直面する課題に沿って具体的な情報を解説しました。
インボイス制度への対応は、単なる事務処理の変更ではなく、取引先との関係や資金繰りにも影響を及ぼす経営戦略上の課題です。
経過措置があるとはいえ、準備が遅れるとビジネス上の不利益に繋がりかねません。
自社の状況を正確に把握し、必要であれば税理士などの専門家の力も借りながら、着実に対応を進めていきましょう。