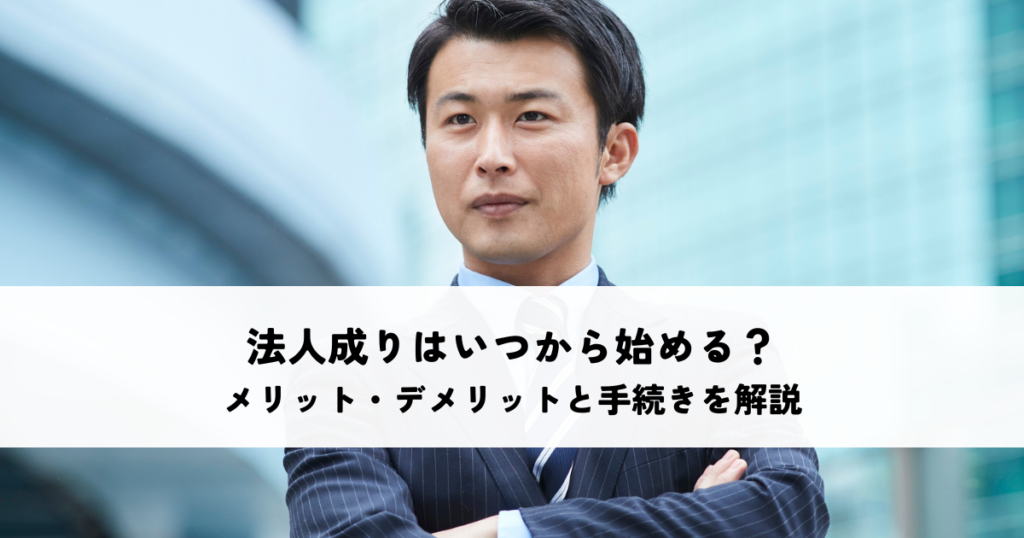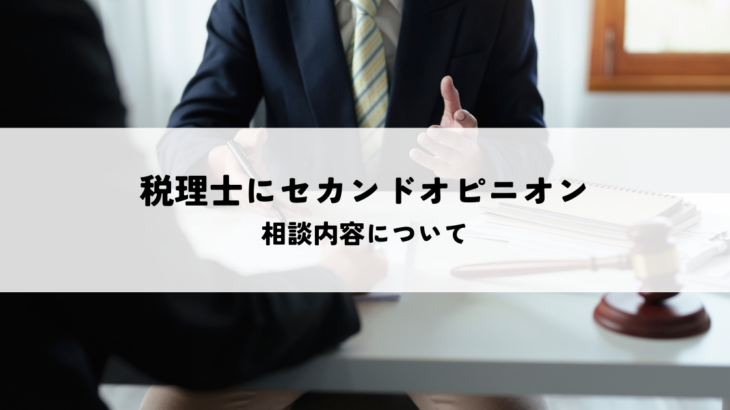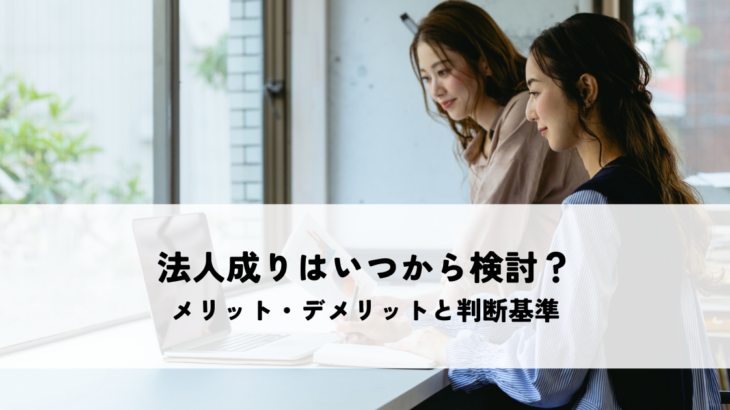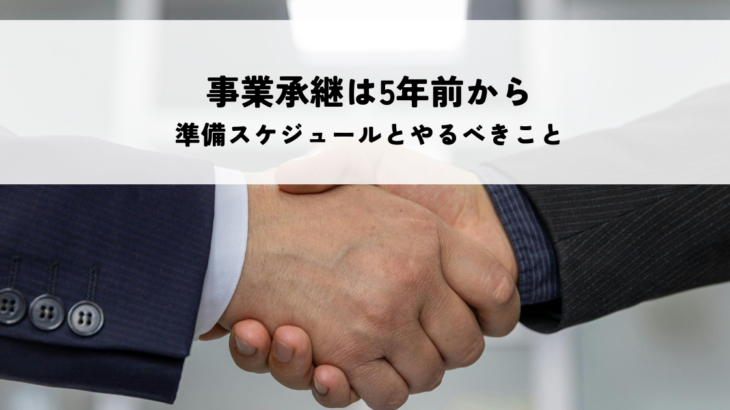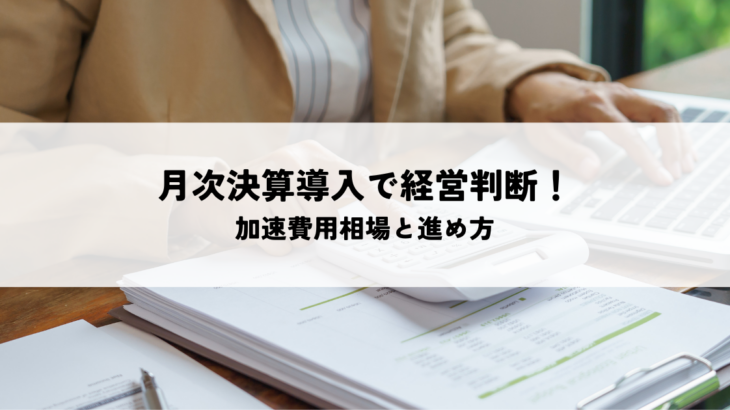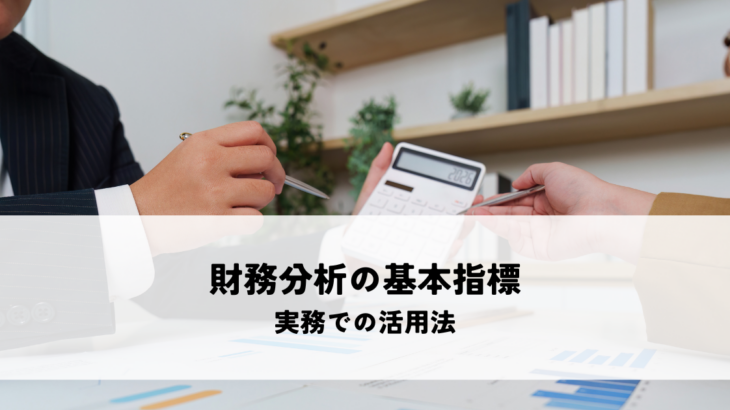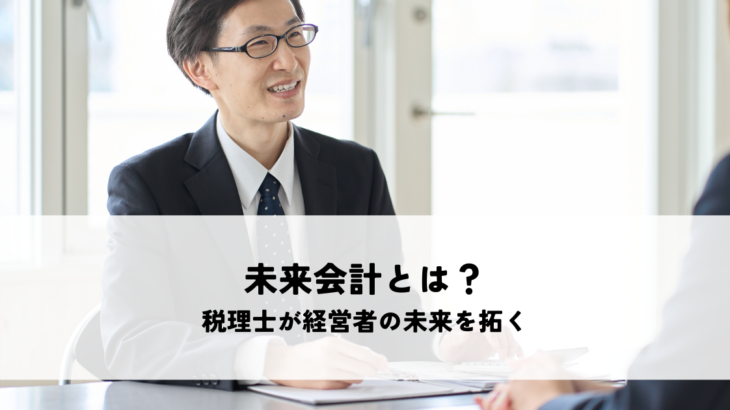事業の成長に伴い、個人事業主が法人へと組織変更する「法人成り」を検討するケースは少なくありません。
しかし、その最適な時期を見極めることは、事業の将来を左右する重要な経営判断であり、決して容易ではありません。事業規模や利益水準、そして将来の事業展望を総合的に考慮し、法人化のメリットとデメリットを慎重に比較検討する必要があります。
今回は、法人成りを検討すべき適切な時期、それによって得られるメリットと直面するデメリット、そして具体的な設立手続きについて詳しく解説します。
法人成りを始める適切な時期
事業開始と同時に法人成りするメリット
事業開始と同時に法人としてスタートする最大のメリットは、設立当初から法人の社会的信用力を得られる点です。
金融機関からの融資審査において有利に働いたり、大企業など取引先によっては法人でなければ契約が難しいケースに対応できたりと、事業の安定的な成長基盤を早期に築ける可能性があります。
ただし、定款認証や設立登記といった初期費用(一般的に株式会社で25万円前後)や、赤字でも発生する法人住民税の均等割、社会保険料の負担といったランニングコストが重くのしかかります。
十分な自己資金や明確な事業計画がなければ、事業が軌道に乗る前に資金繰りが悪化するリスクも孕んでいるため、慎重な判断が求められます。
赤字経営の場合の法人成り
赤字経営が続いている状況での法人成りは、多くの場合、適切な選択とは言えません。
法人化によって節税効果を期待する声もありますが、それは利益が出ていることが前提です。赤字の場合、個人事業主であれば所得税・住民税は発生しませんが、法人は赤字であっても法人住民税の均等割(最低でも年間7万円程度)を納付する義務があります。
赤字を解消し、事業を黒字化させるための具体的な道筋を描くことが最優先であり、法人化の検討は、事業の収益構造が改善し、安定的な黒字が見込めるようになってからが賢明です。
黒字化の見込みが立ったタイミングでの法人成り
事業の黒字化が見え、安定した収益を確保できるようになったタイミングは、法人成りを検討する上で最も一般的で良い時期と言えるでしょう。
法人化に伴うコスト増加を利益で吸収しやすくなり、税制上のメリットを享受できる可能性が高まります。
具体的には、個人事業の「課税所得」が800万円~900万円を超えてくると、所得税・住民税の負担が法人税の負担を上回るケースが多くなるため、この水準が法人化を検討する一つの目安とされています。
税制メリットを最大限に受ける時期
法人成りによって得られる税制上のメリットを最大限に活用できる時期を見極めることも重要です。
例えば、消費税は、資本金1,000万円未満で設立し、特定期間の課税売上高などの要件を満たせば、設立後最大2事業年度にわたって納税が免除される可能性があります。
この免税期間を最大限活用できるよう、事業年度の開始時期を考慮して設立日を決定するなど、税理士などの専門家と相談しながら最適な時期を判断することが、より有利な法人設立に繋がります。

法人成りのメリットとは?
信用力向上による資金調達メリット
法人は、法務局に登記された公的な存在であり、個人事業主と比較して社会的信用力が高まります。
これにより、金融機関からの融資を受けやすくなるだけでなく、より有利な条件での資金調達が期待できます。
また、公共事業の入札参加や、取引先からの信用度が重視される大規模なプロジェクトへの参加もしやすくなり、事業拡大の機会を広げることができます。
法人成りによる節税効果
法人成りによる最大のメリットの一つが節税効果です。
まず、経営者自身への給与(役員報酬)を経費として計上できるため、所得を分散させることができます。また、個人事業主では認められない生命保険料(役員の退職金準備など)や社宅の家賃などを経費として計上できる範囲が広がります。
さらに、個人の所得税が超過累進税率(最大45%)であるのに対し、法人税は一定の税率(資本金1億円以下の中小法人の場合、所得800万円以下の部分は15%)であるため、所得が多くなるほど節税効果は顕著になります。
社会保険加入による福利厚生充実
法人化すると、たとえ社長一人であっても社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられます。
これにより、個人事業主が加入する国民健康保険・国民年金に比べて、病気や怪我の際の傷病手当金や、将来受け取る年金額が手厚くなるなど、経営者自身や従業員の福利厚生が充実します。
これは、従業員の満足度向上や、優秀な人材を採用・維持していく上での大きなアピールポイントとなり、組織力の強化に繋がります。
事業拡大のための基盤構築
法人化は、事業と個人の資産を明確に分離し、会社のガバナンスを強化するための重要なステップです。
これにより、経営の透明性が高まり、将来的な事業承継やM&A、株式公開(IPO)といった、より大きな事業展開を目指すための強固な基盤を構築することに繋がります。
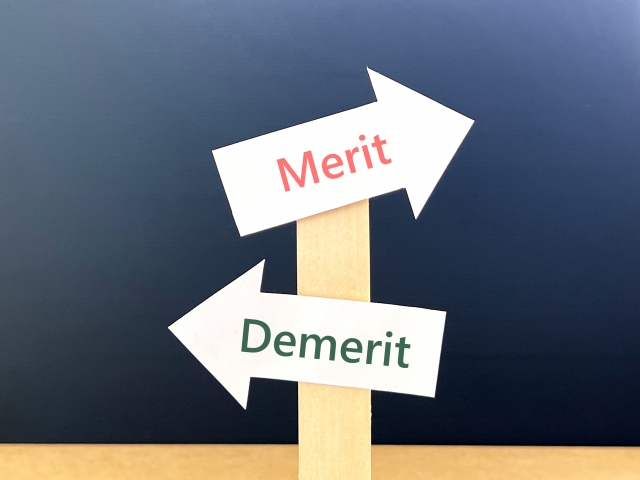
法人成りのデメリットは?
設立費用とランニングコスト増加
法人成りには、前述の通り、株式会社で約25万円、合同会社で約10万円の設立費用がかかります。
加えて、赤字でも発生する法人住民税の均等割、社会保険料の会社負担分、そして会計処理が複雑になることによる税理士への報酬増加など、個人事業主時代にはなかったランニングコストが発生します。
手続きと事務作業の増加
法人は、個人事業主と比較して、社会保険の加入手続きや、株主総会・取締役会の議事録作成、役員変更登記など、法的に求められる手続きや事務作業が格段に増加します。
会計処理も複式簿記が必須となり、より厳格な管理が求められるため、事務負担は確実に増大します。
社会保険加入によるコスト増加
従業員だけでなく経営者自身も社会保険に加入するため、その保険料の約半分を会社が負担する必要があります。
これは従業員の福利厚生向上というメリットの裏返しであり、特に従業員を多く雇用している場合は、会社の資金繰りに大きな影響を与えるコスト増となります。
法人成りの手続き
定款作成と認証
法人設立の第一歩は、会社の憲法とも言える「定款」の作成です。
定款には、商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金の額、発起人の氏名・住所などを記載します。
株式会社の場合、作成した定款を公証役場に持ち込み、その正当性を証明してもらう「認証」手続きが必要です(合同会社の場合は不要)。
設立登記
資本金の払込みなどを終えた後、法務局に会社の設立登記を申請します。
この登記申請日が、会社の設立日となります。
登記には、定款のほか、発起人の決定書、取締役の就任承諾書、印鑑証明書など、多数の書類が必要です。
手続きに間違いがないよう、司法書士などの専門家のサポートを受けるのが一般的です。
税務署への届出
設立登記が完了したら、会社の納税地を管轄する税務署に「法人設立届出書」を提出します。
これに併せて、節税メリットの大きい「青色申告の承認申請書」や、役員報酬を経費にするための「給与支払事務所等の開設届出書」などを提出します。
これらの届出は、その後の税務に大きく影響するため、非常に重要です。
まとめ
法人成りは、事業の成長ステージを大きく前進させる可能性を秘めた重要な決断です。
その最適な時期は、利益水準や今後の事業計画によって千差万別であり、メリットとデメリットを総合的に判断することが不可欠です。
この記事で解説した内容を参考に、まずは自社の現状を正確に把握し、税理士などの専門家と相談しながら、会社にとって最善のタイミングと方法を見つけてください。