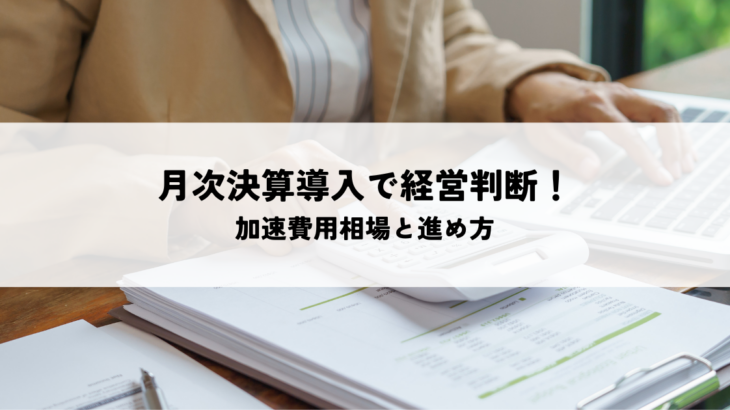将来の資産承継を見据え、計画的に財産を移転させたいとお考えの方にとって、贈与税の非課税枠は非常に有効な手段となります。
特に、相続税の負担を軽減するため、あるいは大切な家族へ早めに財産を託すために、生前贈与の制度を賢く活用したいと考える方は少なくありません。
今回は、利用できる非課税枠の種類とその具体的な金額、そしてそれらを最大限に活かすための実践的な方法について、わかりやすく解説していきます。
生前贈与の非課税枠
基礎控除で年間110万円まで非課税
贈与税の計算方法には、主に「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。
暦年課税を選択した場合、1人の贈与者から1人の受贈者への贈与額が、1年間(1月1日から12月31日まで)で110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
これは「基礎控除」と呼ばれるもので、贈与税の申告も原則不要となります。
この枠は、誰から誰へ贈与されても、贈与者一人あたりではなく、受贈者一人あたりに適用されるため、複数の人から贈与を受ける場合や、複数の人に贈与する場合にも、それぞれの関係で110万円の非課税限度額が適用されます。
相続時精算課税制度の概要と非課税枠
相続時精算課税制度は、65歳以上の親(または祖父母)から20歳以上の子(または孫)への贈与について、累計で2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
この制度を選択すると、それ以降は暦年課税に戻ることができません。
贈与された財産は、贈与者の死亡時に相続財産とみなされ、相続税の課税対象となりますが、2,500万円までは相続税額から控除されるため、実質的に非課税で資産を移転できる可能性があります。
贈与税の計算方法の基本
暦年課税の場合、1年間(1月1日~12月31日)の贈与額の合計から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して贈与税が課税されます。
例えば、1年間に200万円の贈与を受けた場合、200万円から110万円を引いた90万円が課税対象となり、この90万円に所定の税率(一般贈与財産で10%~55%)をかけて計算します。
相続時精算課税制度を選択している場合は、累計2,500万円までは非課税となり、2,500万円を超えた部分に対して一律20%の税率で計算されます。

毎年110万円の非課税枠の賢い活用法
長期にわたる計画的な贈与で相続財産を減らす
毎年110万円の基礎控除枠を毎年活用することで、時間をかけて着実に相続財産を減らすことができます。
例えば、10年かけて1,100万円(110万円×10年)を贈与した場合、その財産は贈与者の相続財産から減額されることになります。
ただし、相続開始前7年以内(2024年1月1日以降は17年以内)に贈与された財産は相続税の算定基礎に加算されるため、相続直前の贈与ではなく、長期的な視点で計画的に行うことが、相続税の総額を抑える上で重要となります。
孫への贈与も非課税枠を活用できる
生前贈与の非課税枠は、子だけでなく孫にも適用可能です。
暦年課税制度を利用すれば、孫一人あたり年間110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。
孫に直接財産を贈与することで、将来の世代への円滑な資産移転を図ることができます。
特に、孫が将来的に親(子)から相続する財産を考慮すると、祖父母から孫への直接贈与は、世代間の相続税負担を平準化する有効な手段となり得ます。
贈与の記録を適切に残す重要性
毎年110万円の基礎控除枠を活用していても、毎年同額を同じ時期に贈与していると、税務署から「定期贈与」とみなされ、110万円の控除が毎年適用されず、初年度の贈与額全体に贈与税が課税されるリスクがあります。
このリスクを避けるため、贈与契約書を作成し、贈与の意思表示を明確にすること、そして、振込明細や通帳などの記録を適切に保管することが極めて重要です。

住宅購入・教育資金贈与の特例制度とは
住宅取得等資金贈与の特例の概要と上限額
この特例制度は、親や祖父母が、子や孫の住宅の新築・購入・増改築などのために資金を贈与する場合に利用できます。
一定の期間(例えば2024年1月1日から2025年12月31日まで)に適用され、省エネ等性能の高い住宅であれば最大1,500万円、それ以外の住宅でも最大1,000万円まで、非課税で贈与することが可能です。
この特例枠は、暦年課税の基礎控除110万円とは別に利用できます。
教育資金贈与の特例の概要と上限額
この特例制度は、祖父母などが、孫など(30歳未満)の教育資金(学校の入学金・授業料、習い事の月謝など)として、最大1,500万円までを非課税で贈与できる制度です。
贈与された資金は、信託銀行などの金融機関に信託され、教育資金としてのみ使用が管理されます。
この制度を利用することで、まとまった教育資金を贈与税の心配なく準備できます。
各特例制度の適用要件と注意点
住宅取得等資金贈与の特例では、受贈者が20歳以上であること、日本国内に居住していること、一定の品質・性能基準を満たす住宅であることなどが主な要件です。
教育資金贈与の特例では、受贈者が30歳未満で、教育資金としてしか使えないこと、そして、30歳に達した時点で使いきれなかった資金や、教育資金以外の目的で使われた資金には贈与税がかかる点に注意が必要です。
また、どちらの特例制度を利用した場合でも、相続開始前7年以内(2024年1月1日以降は17年以内)の贈与は相続財産に加算されるため、相続税の計算にも影響します。
贈与税の課税リスクを避けるには
定期贈与とみなされないための方法
毎年決まった時期に、決まった金額を贈与し続けると、税務署はそれを「定期贈与」とみなし、贈与契約が毎年更新されているのではなく、最初から一定期間にわたって贈与を受ける約束があると判断する可能性があります。
この場合、110万円の基礎控除は毎年適用されず、当初の贈与額全体に課税されることがあります。
これを避けるためには、贈与する金額や時期を毎回事ごとに変える、贈与契約書を毎年締結し直す(あるいは自動更新条項のない契約書にする)、贈与の意思表示を文書で行うなどの工夫が必要です。
贈与の事実を明確にするための証拠保全
税務調査が入った際に、贈与が正しく行われたことを証明するためには、客観的な証拠が不可欠です。
具体的には、当事者の意思確認、贈与額、贈与日、贈与の目的などを明記した「贈与契約書」を作成することが推奨されます。
また、銀行口座間の振込明細や通帳の記録、贈与者から受贈者への手紙やメールなど、贈与の意思と実行があったことを示す記録を大切に保管しておくことが重要です。
贈与税申告の必要性と期限
贈与税の申告は、基礎控除額(暦年課税の110万円)や相続時精算課税制度の非課税枠(2,500万円)を超えた場合、あるいは住宅取得等資金贈与や教育資金贈与の特例制度を利用した場合に必要となります。
これらの非課税枠や特例制度は、自動的に適用されるものではなく、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署への申告と納税が求められます。
申告を怠ると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があるため、期限内の手続きが肝要です。
まとめ
生前贈与における非課税枠は、将来の相続税負担を軽減するための有効な手段です。
年間110万円の基礎控除枠を計画的に活用することや、住宅・教育資金贈与の特例制度を理解し適用することで、より効果的な資産移転が可能となります。
一方で、定期贈与とみなされるリスクや申告漏れといった課税リスクを避けるため、贈与の記録を適切に残し、申告期限を守ることが不可欠です。
専門家への相談も視野に入れつつ、ご自身の状況に合わせた計画的な贈与を行いましょう。