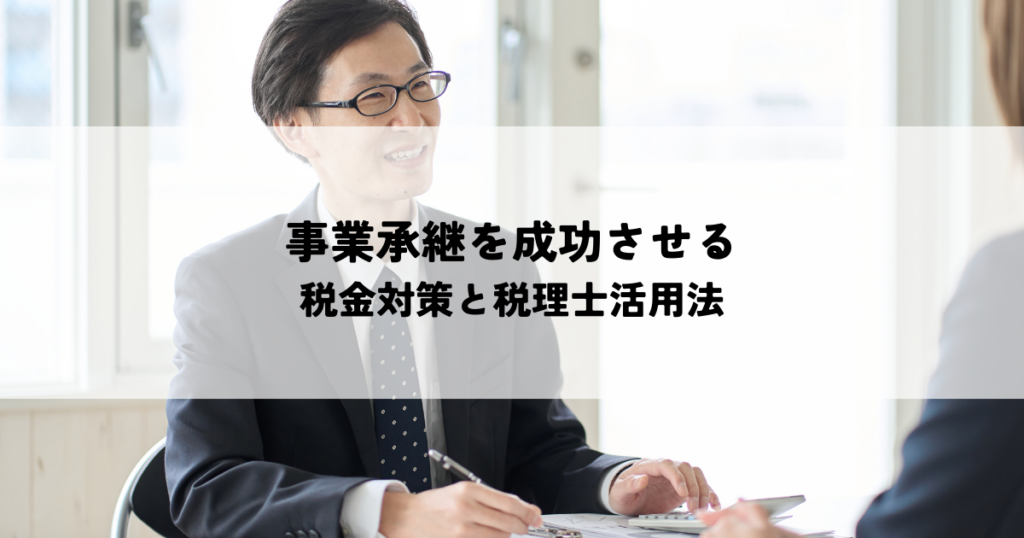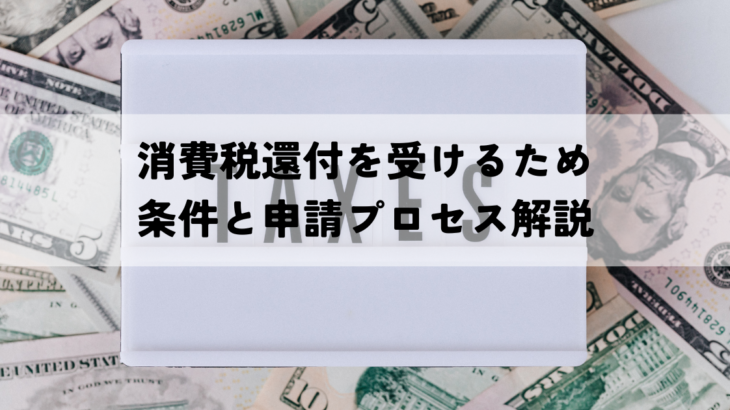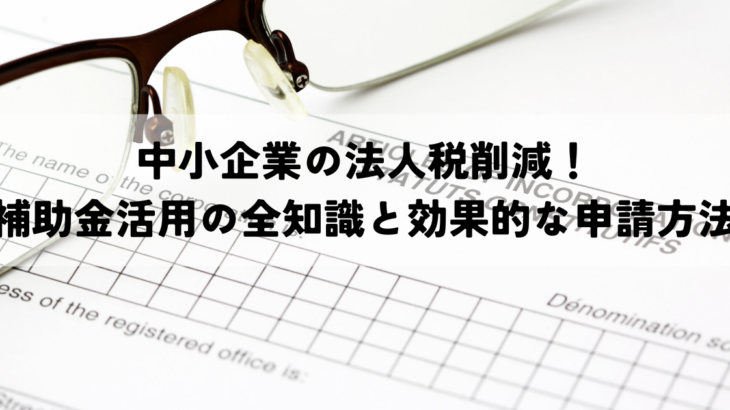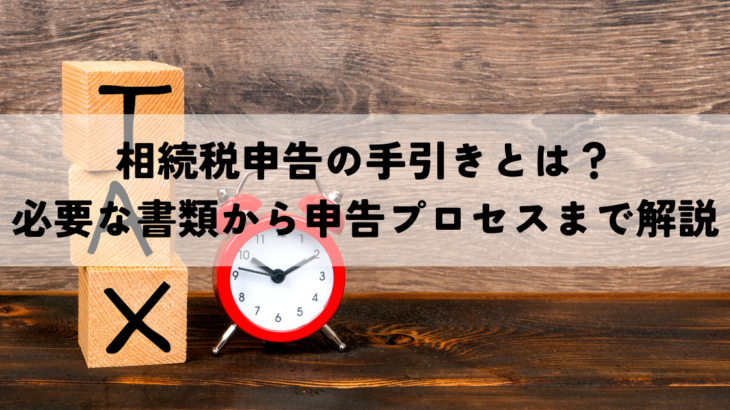事業承継は、企業の存続と将来の発展を左右する極めて重要な経営課題であり、そのプロセスにおいて複雑な税金問題は避けて通れません。
しかし、事前に適切な税務対策を計画的に講じることで、後継者が背負う多大な税負担を大幅に軽減し、経営基盤を揺るがすことなく円滑な承継を実現することが可能です。
今回は、事業承継の主要なパターンとそれに伴い発生する税金の種類、具体的な節税対策、そしてこの難題を乗り越えるためのパートナーとなる信頼できる税理士の選び方について詳しく解説します。
事業承継の種類と税金
親族内承継における税金
親族内承継は、経営者の子や配偶者など、事業を家族内で引き継ぐ最も一般的な方法です。
この場合、資産の移転方法に応じて贈与税または相続税が課税される可能性があります。
贈与税は、経営者が存命中に後継者へ自社株式や事業用資産を渡す、いわゆる生前贈与によって事業を承継する場合に発生します。
一方で相続税は、経営者の死亡をきっかけとして、相続人が遺産として事業を承継する場合に発生します。
課税対象となるのは、単純な預貯金だけでなく、事業の価値そのものを算定した評価額や、会社が所有する資産の評価額となります。
具体的には、工場や店舗といった事業用不動産や機械などの事業用設備、そして長年培ってきたブランド力や顧客網といった営業権(のれん)なども評価対象となり、個々の企業の状況に応じて算出される税額は大きく変動します。
特に非上場株式の評価額の算出方法は極めて複雑なため、税理士などの専門家による正確な評価を受けることが不可欠です。
例えば、会社の純資産、過去の利益、そして類似する上場企業の株価などを基に多角的な評価が行われます。
また、相続税の申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と厳格に定められています。
この短期間に全ての財産評価と手続きを完了させる必要があるため、早期の準備が求められます。
親族外承継における税金
親族外承継とは、親族以外の役員や従業員、あるいは全くの第三者や外部企業に事業を承継する方法を指します。
これには、役員・従業員への承継(EBO・MBO)や、第三者への売却であるM&A(合併・買収)、株式譲渡などが該当します。
この場合、事業を売却した対価(利益)に対して譲渡所得税が課税されることが一般的です。
譲渡所得税は、事業を譲渡したことで得られた利益、つまり売却価格からその資産の取得にかかった費用やM&Aの仲介手数料などを差し引いた金額に対して課税される税金です。
この譲渡によって生じた利益は「譲渡所得」として他の所得とは分離して計算され、所定の税率が適用されます。
譲渡所得税の計算においては、特に創業から長い年月が経過している場合など、資産の取得費用が不明確なケースもあり、税理士といった専門家の助言が必要となることも少なくありません。
特に、事業そのものの価値(評価額)を算定する際には、将来期待される収益性や業界の市場環境などを客観的に分析した上で、複雑な計算を行う必要があります。
M&Aによる事業承継における税金
M&Aの手法を用いて事業承継を行う場合、その具体的なスキームによって譲渡所得税や法人税、登録免許税、消費税など、多種多様な税金が発生する可能性があります。
どのような税金が、誰に、いくら課されるかは、M&Aの方法(株式譲渡か、事業譲渡かなど)や詳細な取引構造によって大きく異なります。
例えば、会社のオーナーが保有する株式を買い手に売却する「株式譲渡」の場合は、売却益に対してオーナー個人に譲渡所得税が課税されます。
一方、会社がその事業の一部または全部を買い手に売却する「事業譲渡」の場合は、譲渡した資産の種類に応じて消費税が課税されるほか、売却益は譲渡した会社の法人所得となり、法人税の課税対象となります。
また、M&Aの実行に際して発生する弁護士費用やデューデリジェンス費用なども、税金の計算に影響を与える要素となります。
これらの税金計算は非常に複雑で専門性が高いため、M&Aの実績が豊富な税理士などの専門家へ事前に相談することが極めて重要です。
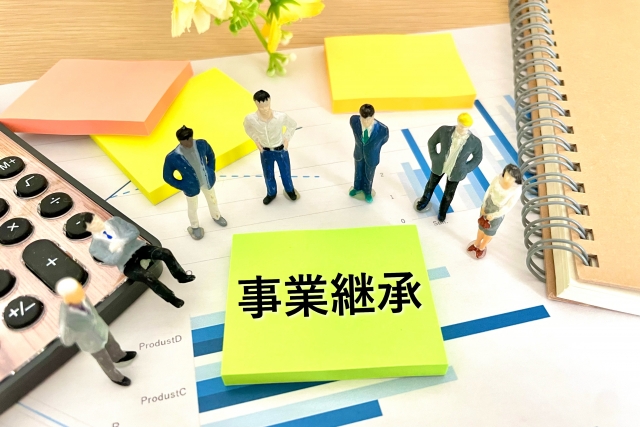
事業承継で使える節税対策には何がある?
贈与税の特例を活用した節税
後継者へ生前贈与を行う場合、税法で定められた贈与税の特例を有効に活用することで、税負担を大きく軽減できる可能性があります。
具体的には、事業用の土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」や、事業用資産の贈与に関する各種特例などが存在します。
小規模宅地等の特例は、後継者が事業を引き継ぎ、その土地を継続して使用するなど一定の条件を満たす場合に、相続税や贈与税の課税評価額を大幅に圧縮できる制度です。
また、事業承継税制の前提となる「事業用資産の贈与に関する特例」などを活用することで、贈与税の負担を抑えながら計画的に資産を移転させることが可能です。
これらの特例を活用することで、納税のために事業用資産を売却するといった事態を避け、円滑な事業承継を進めることが可能になります。
ただし、いずれの特例も適用を受けるためには非常に細かい条件を満たす必要があるため、必ず税理士に相談して自社が適用要件に合致するかどうかを事前に確認することが大切です。
納税猶予制度を活用した節税
相続や贈与によって多額の税金が発生したものの、手元に納税資金が不足している場合、納税猶予制度を利用することで、税負担を軽減し、当面の資金繰りを安定させることができます。
この制度は、あくまで納税を先延ばしにするものであり免除ではありませんが、一時的な資金不足を解消し、事業の継続を最優先に考えられるようにする制度です。
納税が猶予される期間や適用条件は、承継する財産の状況や納税者の経済状況などを総合的に考慮して個別に決定されます。
なお、猶予期間中は、担保の提供が必要となるほか、年率に応じた利子税を支払う必要があります。
猶予期間が満了した後には、猶予されていた相続税をまとめて支払う必要がありますが、その間に事業が安定的に継続していれば、納税資金を計画的に準備しやすくなります。
事業承継税制を利用した節税
事業承継税制は、後継者不足に悩む中小企業の円滑な事業承継を国が後押しするために設けられた、非常に強力な制度です。
一定の要件を満たすことでこの制度を利用すれば、後継者が相続または贈与によって取得した非上場株式等に係る相続税や贈与税の納税が100%猶予され、さらに将来、次の代へ承継するなどの要件を満たせば、その税額が最終的に免除されることも可能です。
ただし、事業承継税制の適用を受けるための要件は非常に厳格に定められており、都道府県への特例承継計画の提出や、承継後5年間の雇用維持などが必要なため、税理士などの専門家に相談し、適用要件を確実に満たしているかを確認することが極めて重要です。
この制度は、適用要件さえ満たせば、後継者の税負担を実質的にゼロにできる可能性があるため、中小企業の事業承継においてはまず検討すべき選択肢と言えます。
事業承継に強い税理士の選び方
事業承継に精通した税理士を見つける
事業承継は、通常の税務申告とは異なり、資産評価、相続、M&Aなど、税務上の複雑な問題を多く含むため、これらの分野に精通した税理士をパートナーとして選ぶことが成功の鍵となります。
事業承継に関する専門的な知識や豊富な実務経験を持つ税理士は、個々の企業に合った最適な税金対策の提案や、複雑な手続きの代行など、的確で心強いアドバイスを提供してくれます。
税理士の専門性を確認するには、事務所のホームページに掲載されている取扱業務や過去の実績、あるいは経営者仲間からの紹介や口コミなどを参考にすることができます。
また、地域の税理士会に問い合わせて、事業承継に強い税理士を紹介してもらうことも有効な手段の一つです。
税理士との適切なコミュニケーション方法
信頼できる税理士を見つけた後、円滑なコミュニケーションを築くことは、事業承継を成功させる上で不可欠な要素です。
税理士に対して、会社の現状や後継者に関する悩み、将来の事業計画などを包み隠さず詳細に説明し、少しでも疑問や不安に思う点を率直に質問することで、より実態に即した適切なアドバイスを受けることができます。
初回の相談で相性を確かめるとともに、契約後は定期的な面談や、メール、電話など、様々なコミュニケーション手段を柔軟に活用することで、常に情報を共有し、密接な連携体制を築きましょう。

事業承継の税務相談窓口
税務署への相談方法
全国の税務署は、税金に関するあらゆる一般的な質問に対応する公的な相談窓口として利用できます。
ただし、税務署の職員は税法の専門家ではありますが、個別の事情が複雑に絡み合う事業承継に関する専門的なコンサルティング知識までを持つとは限りません。
そのため、一般的な制度の概要を知りたい場合には有用ですが、自社にとって最適なプランニングといった複雑な税務問題については、やはり税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
税務署への相談は、事前の予約が必要な場合が多いため、電話や国税庁のウェブサイトで確認してから来所するようにしましょう。
税理士事務所への相談方法
税理士事務所は、事業承継に関する高度で専門的な知識と経験を持つ税理士が在籍しているため、税務相談を行う上で最も的確かつ最適な窓口となります。
税理士に相談する際には、事前に決算書や会社の定款、株主名簿などを用意し、事業の状況や承継に関する希望、疑問点などを具体的に説明できるように準備しておきましょう。
信頼できる税理士は、現状を丁寧にヒアリングした上で、事業承継に最適な税務対策を複数提案し、その実行まで責任を持ってサポートしてくれます。
事業承継相談センターの活用
各都道府県には、国が設置する「事業承継・引継ぎ支援センター」があり、事業承継に関するあらゆる相談にワンストップで対応しています。
これらの公的機関では、専門家による無料相談なども定期的に行われているため、事業承継について何から手をつけて良いか分からない場合など、初めて相談する際には積極的に利用を検討してみましょう。
まとめ
事業承継は、税金問題と密接不可分な関係にあり、その対策の巧拙は、会社の存続と後継者の未来に大きく影響します。
今回解説したように、事業承継には様々なパターンがあり、それぞれで課される税金や有効な節税対策は異なります。
円滑な事業承継の実現のためには、経営者が元気なうちから早期に準備を始め、専門家から客観的なアドバイスを受けることが何よりも不可欠です。
信頼できる税理士や事業承継・引継ぎ支援センターなどを積極的に活用し、自社にとって最適な税務対策を講じることで、未来へ続く円滑な事業承継を実現しましょう。