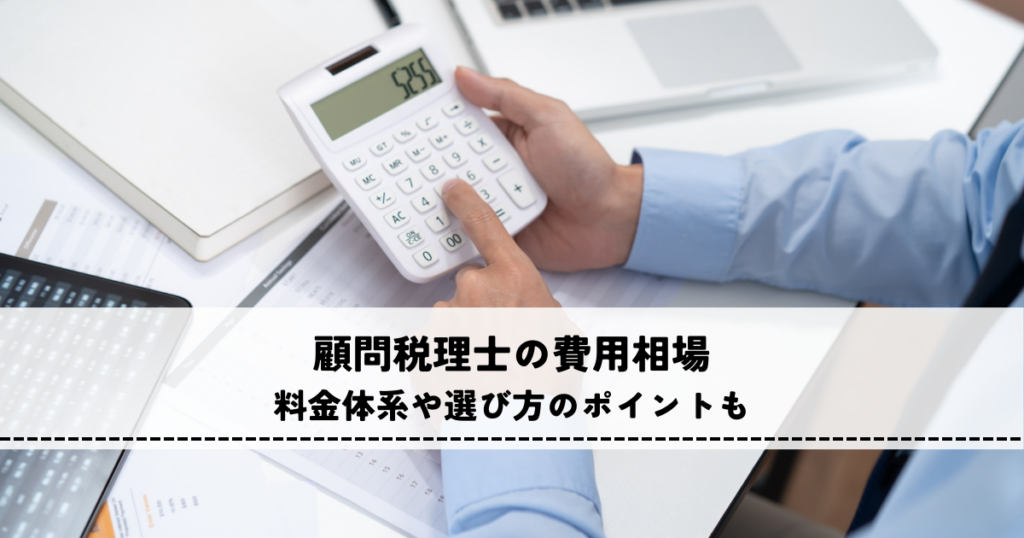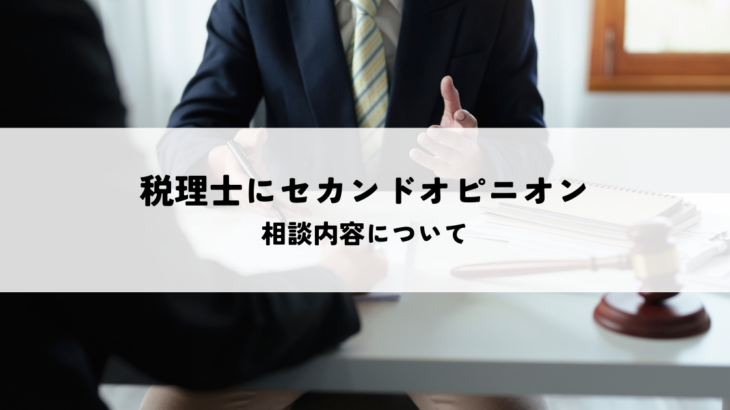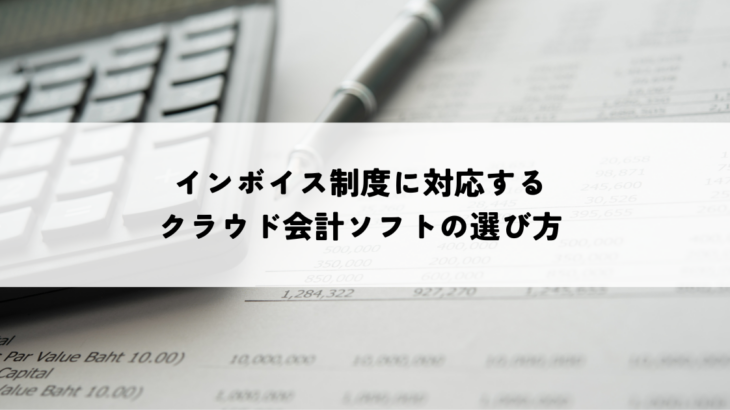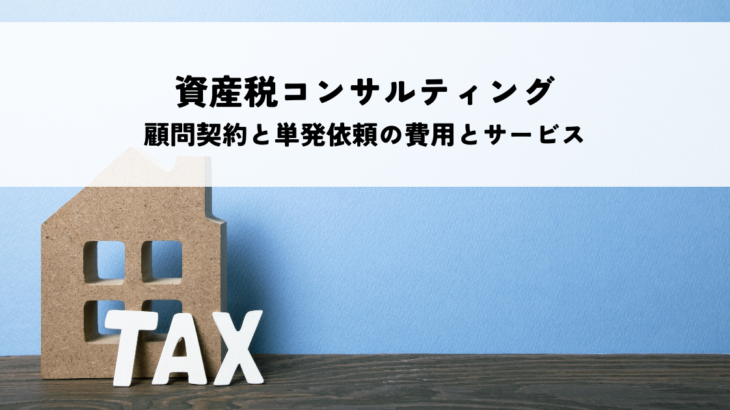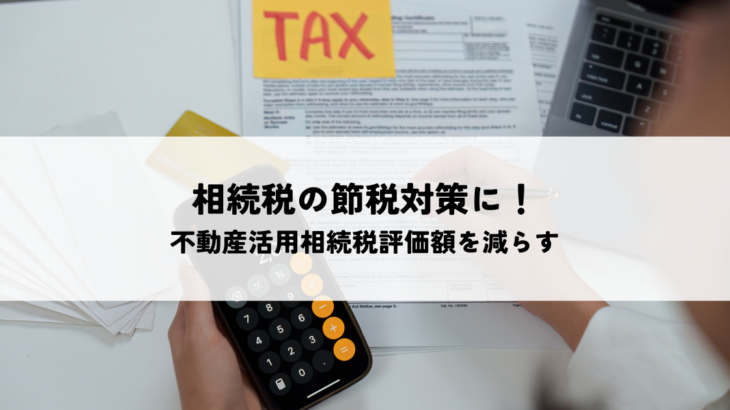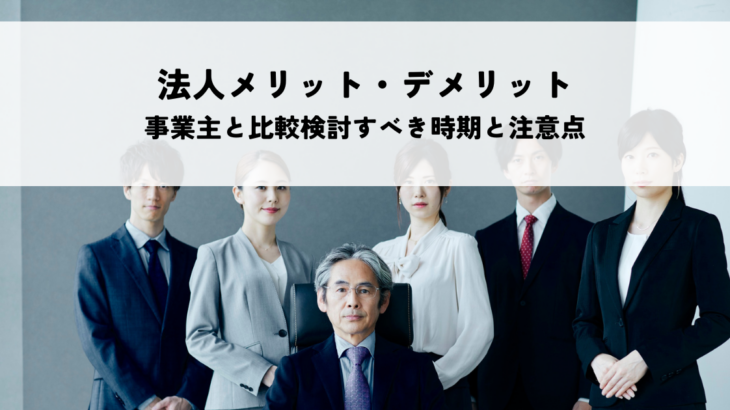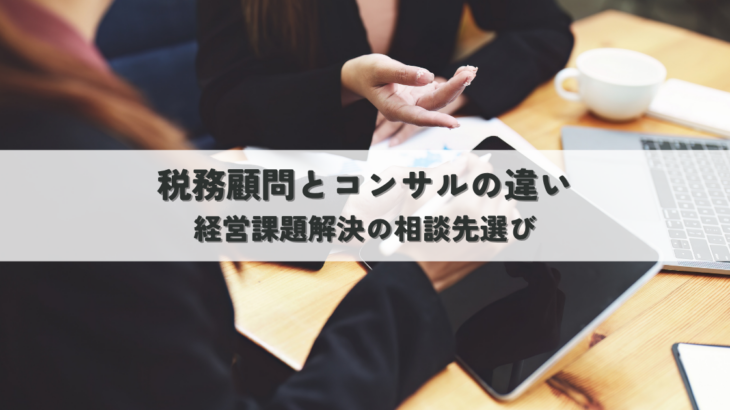顧問税理士を探す際、その専門性や相性と並んで、費用は最も重要な検討事項の一つです。
税理士への報酬は単なるコストではなく、適正な税務申告によるコンプライアンスの担保、効果的な節税、そして健全な経営判断を下すための「投資」と捉えるべきです。
今回は、顧問税理士の料金がどのように決まるのか、その相場や具体的な料金体系、そして費用対効果の高い税理士を選ぶためのポイントについて、より詳しく掘り下げて情報を提供します。
顧問税理士の相場
相場は月額2万円~10万円程度
これはあくまで大まかな目安であり、顧問料は会社の年間売上高、従業員数、業種、そして依頼するサービス内容によって大きく変動します。
個人事業主や設立間もない法人であれば月額2万円台から、一般的な中小企業であれば月額3万円~5万円程度がボリュームゾーンとなります。
従業員数が増え、取引が複雑化する年商数億円規模の企業になると、月額5万円~10万円程度になることも珍しくありません。
さらに、連結納税や国際税務など高度な専門性が必要となる上場企業やその子会社では、月額10万円を大きく超えるケースも一般的です。
会社の規模が大きくなるほど顧問料が高くなる傾向
これは、会社の規模に比例して税理士が確認すべき取引量や会計処理の複雑さが増し、税務リスクも高まるためです。
税理士事務所が見積もりを算出する際は、主に「年間売上高」「従業員数」「月間の仕訳数(取引の件数)」といった客観的な指標を基準にします。
例えば、従業員数が多ければ給与計算や年末調整の業務負担が大きくなり、売上高や取引件数が多ければ、それだけ帳簿のチェックや税務判断に要する時間が増加するため、顧問料も高くなるのです。
業種やサービス内容による料金の変動
例えば、建設業や不動産業は、工事進行基準といった特殊な会計処理や複雑な消費税の取り扱いが求められるため、他の業種に比べて顧問料が高めに設定される傾向があります。
一方、取引が比較的シンプルなIT企業やサービス業は、顧問料が安めになることが多いです。ただし、ECサイト運営のように取引件数が膨大な場合や、SaaSビジネスのような複雑な収益認識基準が必要な場合はこの限りではありません。
さらに、月次決算の早期化支援、経営分析資料の作成、資金調達支援といった、付加価値の高いサービスを顧問契約に含める場合、その分料金は高くなります。
初期費用は0円~10万円程度
初期費用は税理士事務所の方針によって異なり、キャンペーンなどで無料としている事務所もあります。
一般的に初期費用が発生する場合、その内訳は、過去の決算書の分析、会計ソフトへのデータ移行や初期設定、今後の経理業務のフロー構築に関するコンサルティング費用などが含まれます。
契約時にこれらの作業を丁寧に行うことで、その後の顧問業務がスムーズに進むという側面があります。

顧問税理士の料金体系はどうなっている?
顧問料は基本料金+オプション料金
多くの税理士事務所では、料金体系を明確にするため、基本となる顧問料と、必要に応じて追加するオプションサービスを分けています。
基本料金には、税務・会計に関する電話やメールでの相談、自社で作成した会計帳簿のレビューなどが含まれるのが一般的です。
オプション料金としては、記帳代行、給与計算、社会保険手続き、経営会議への参加などが用意されており、自社のニーズに合わせて組み合わせることができます。
記帳代行や給与計算代行はオプション料金
これらの定型的な業務は、多くの税理士事務所がオプションとして提供しています。
記帳代行の料金は、月々の仕訳数(100仕訳まで〇円、以降50仕訳ごとに△円など)に応じて変動する従量課金制が一般的です。
また、給与計算代行は、従業員一人あたり〇円といった形で料金が設定されていることが多く、自社で対応する人件費と比較検討することが重要です。
契約前に、どこまでの業務が基本料金に含まれるのかを必ず確認しましょう。
決算料や年末調整費用は別途請求されるケースも
法人税や消費税の申告書作成・提出を行う「決算申告」は、年に一度の非常に重要な作業であり、多くの時間と専門的な知識を要します。
そのため、月々の顧問料とは別に「決算料」として、月額顧問料の4~6ヶ月分程度が請求されるのが一般的です。
同様に、従業員の所得税を精算する年末調整業務も、基本料金のほかに別途費用が発生することが多いです。
税務調査の対応費用は別途請求
税務署による税務調査が行われる場合、その対応は顧問税理士にとって非常に重要かつ負担の大きい業務です。
調査前の準備、調査当日の立ち会い、調査後の税務署との折衝など、専門的な対応が必要となるため、顧問料とは別に費用が請求されます。
料金は、税理士の日当(1日あたり5万円~15万円程度が目安)で計算されることが一般的です。

業種別の顧問税理士の相場
建設業や不動産業
これらの業種は、案件ごとの原価計算や工事進行基準の適用、不動産取引に伴う消費税や印紙税の複雑な判断など、専門的な会計・税務知識が不可欠です。
そのため、必然的に税理士の業務負担が重くなり、他の業種に比べて顧問料が高めに設定される傾向があります。
IT企業やサービス業
これらの業種は、在庫管理が不要で、会計処理が比較的シンプルであることが多いです。
そのため、税理士のチェック業務の負担が軽く、顧問料が安めに収まる傾向があります。
ただし、前述の通り、取引件数が極端に多い場合や、海外との取引がある場合などは、料金が高くなることもあります。
医療法人や社会福祉法人
医療法人や社会福祉法人は、一般企業とは異なる独自の会計基準や、都道府県への定期的な届出義務、複雑な社会保険診療報酬の計算など、極めて高い専門性が求められます。
これらの分野に精通した税理士は限られているため、その希少価値から顧問料も高額になる傾向があります。
顧問税理士を選ぶ際のポイント
税理士の専門分野や得意業種
税理士には、相続に強い、国際税務が得意、IT業界に精通しているなど、それぞれの専門分野や得意業種があります。
自社の業種や抱えている課題に合致した税理士を選ぶことが、的確なアドバイスを受けるための第一歩です。
事務所のウェブサイトで、同業種の顧客実績や関連する情報発信(ブログ記事など)があるかを確認しましょう。
税理士との相性
税理士は、会社の財務状況という最も重要な情報を共有し、経営の悩みを相談するパートナーです。
専門的な内容を分かりやすい言葉で説明してくれるか、質問しやすい雰囲気か、経営者のビジョンに共感してくれるかなど、初回相談の際にご自身の感覚で相性を確かめることが非常に重要です。
信頼関係を築ける税理士を選ぶことが、円滑な経営に直結します。
料金体系やサービス内容
後々のトラブルを避けるため、契約前に必ず書面で見積書や契約書を提示してもらい、料金体系とサービス内容を隅々まで確認しましょう。
「どこまでの業務が顧問料に含まれるのか」「追加料金が発生するのはどのような場合か」「契約期間や解約条件はどうなっているか」など、不明な点は遠慮なく質問し、全てクリアにしてから契約することが大切です。
まとめ
今回は、顧問税理士の料金相場、料金体系、業種別の傾向、そして選び方のポイントについて具体的に解説しました。
顧問税理士の費用は、企業規模、業種、依頼するサービス内容など、様々な要因によって決まります。
単に料金の安さだけで選ぶのではなく、自社の成長を長期的にサポートしてくれるパートナーとしてふさわしいかという視点が不可欠です。
必ず複数の税理士事務所から見積もりを取り、料金だけでなく、提供されるサービスの価値や担当者との相性を総合的に比較検討し、納得のいく税理士を選びましょう。