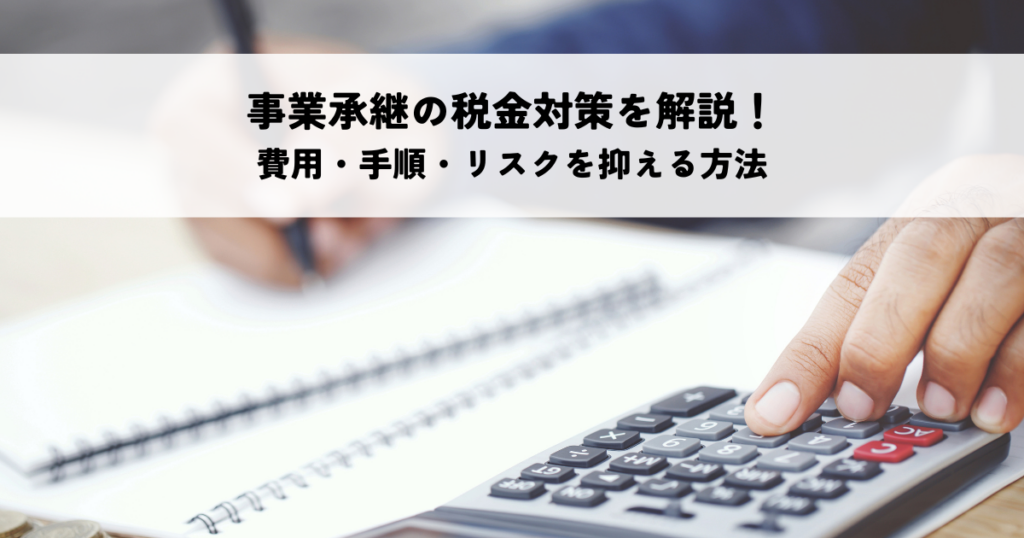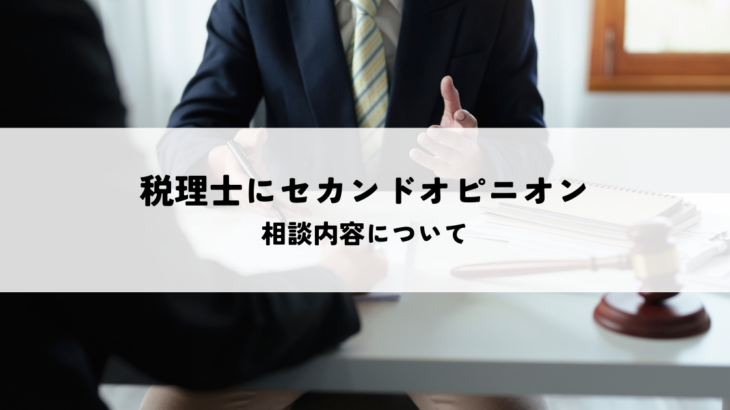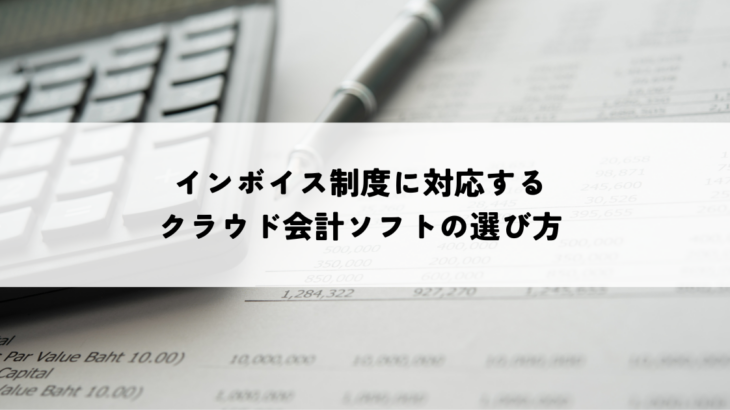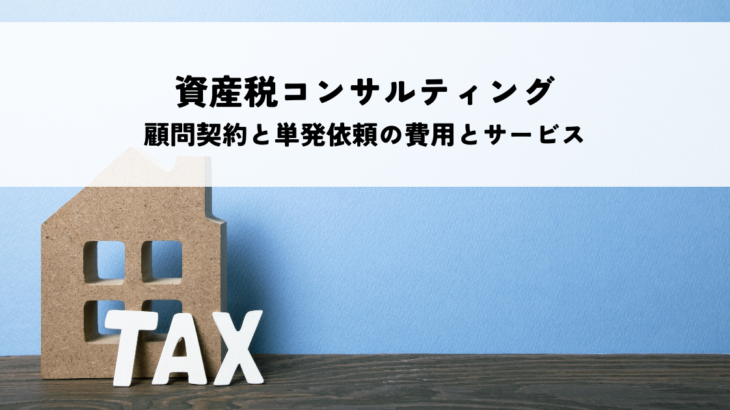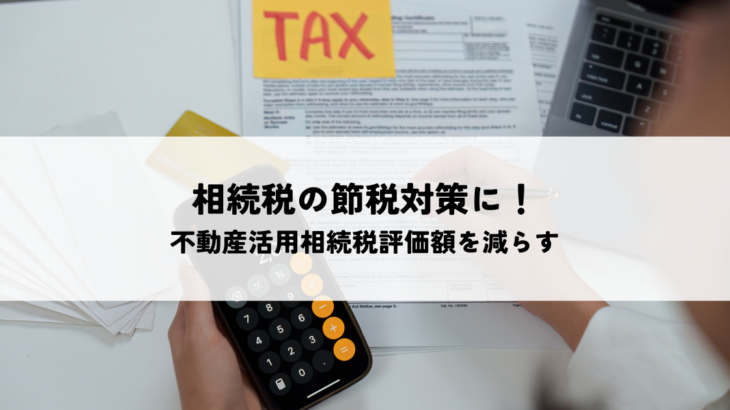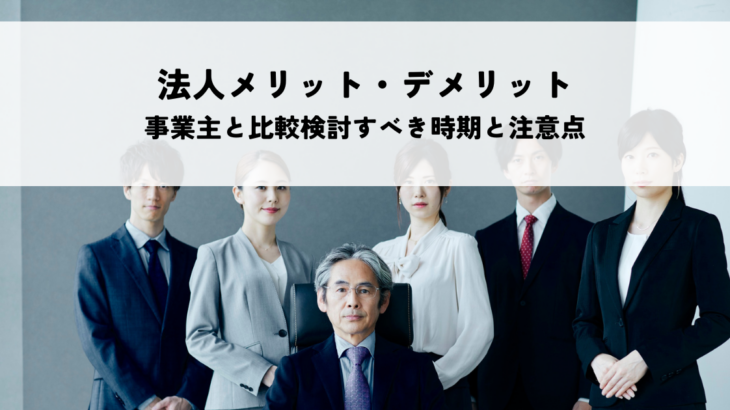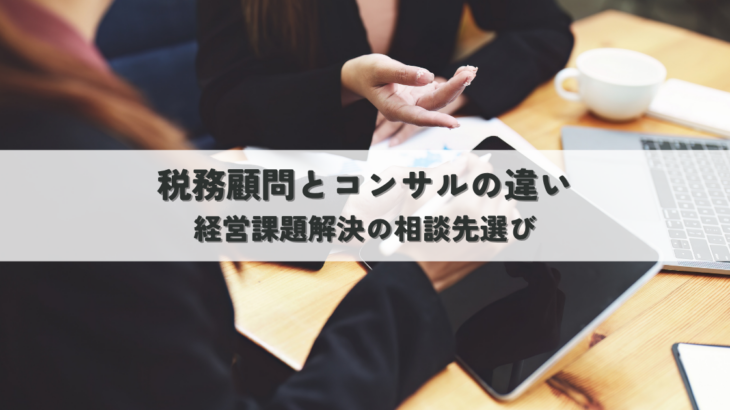事業承継は、創業者が築き上げた会社を次世代へと引き継ぎ、その存続と発展を託す、経営者人生における最大のイベントの一つです。
それは単なる財産の相続ではなく、経営権、従業員の雇用、取引先との信頼関係といった、企業の全てを引き継ぐ一大プロジェクトと言えます。
円滑な承継を実現するためには、5年、10年単位での綿密な準備と計画が不可欠であり、その中でも後継者が直面する「納税資金の確保」は極めて大きな課題となります。
納税資金を準備できずに、やむなく廃業や会社売却を選択するケースも少なくありません。
今回は、事業承継の成否を分ける納税資金計画に焦点を当て、承継にかかる税金の種類と計算方法、具体的な計画立案の手順、そして多様な資金調達方法について詳しく解説します。
事業承継にかかる税金の種類と税額の計算方法
相続税の計算方法と試算例
親族内承継において、相続による引き継ぎは最も大きな税負担となる可能性があります。
相続税の計算は、まず全ての相続財産の評価額を合計し、そこから基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて課税遺産総額を算出します。
この金額を基に、法定相続分に応じた税率を適用して税額を計算します。
相続財産には、現預金や個人所有の不動産だけでなく、事業そのものの評価額(具体的には非上場株式の評価額)が含まれます。
この自社株の評価は、類似業種比準価額方式や純資産価額方式など複数の複雑な計算方法があり、専門家である税理士の腕の見せ所でもあります。
例えば、事業評価額が1億円、その他の相続財産が5,000万円、相続人が3人(配偶者、子2人)の場合、基礎控除額は4,800万円となり、課税遺産総額は1億200万円(1.5億円 – 4,800万円)です。
これに対して高額な相続税が発生することが予想されます。
贈与税の計算方法と試算例
後継者へ生前に株式などを贈与する場合、贈与税の納税義務が生じます。
贈与税の計算は、1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産の価額から基礎控除額110万円(暦年贈与)を差し引いた金額に、税率を乗じて算出します。
この暦年贈与を長期にわたり活用することで相続税の節税を図ることが可能ですが、税率が相続税より高く設定されているため、一度に高額な贈与を行うと多額の納税義務を負うことになります。
また、「相続時精算課税制度」を選択すれば、2,500万円まで贈与税がかからずに財産を移転できますが、その贈与財産は相続時に相続財産に加算して相続税を計算するため、直接的な節税効果は限定的です。
しかし、早期に株式を後継者に集中させたい場合には有効な手段となります。
事業承継に関連するその他の税金
相続税や贈与税以外にも、事業承継のスキームによっては様々な税金が関連してきます。
例えば、後継者が株式を買い取る資金を捻出するために先代経営者が個人所有の土地や建物を売却すれば「譲渡所得税」がかかります。また、不動産を贈与した場合には、相続で引き継ぐ場合に比べて高額な「登録免許税」や「不動産取得税」が後継者に課されます。
これらの付随する税金についても、事前に専門家と相談し、承継方法ごとのトータルコストを比較検討することが重要です。

納税資金計画の具体的な手順は?
現状分析事業の財務状況と相続財産の把握
納税資金計画の第一歩は、現状を正確に把握することです。
会社の貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を分析し、自社株の評価額や収益力を評価します。
同時に、経営者個人が所有する不動産、有価証券、生命保険、そして会社への貸付金といった全ての相続財産をリストアップし、その価値を正確に把握する必要があります。
特に中小企業の経営者は、個人と法人の資産が複雑に絡み合っていることが多いため、専門家による客観的な棚卸しが不可欠です。
目標設定必要な納税資金の総額を試算
現状分析で把握した財産評価額に基づき、相続税や贈与税、その他の関連税金の総額をシミュレーションします。
相続税の納税期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と非常に短いため、この短期間で準備すべき現金の総額を明確な目標として設定することが重要です。
この試算は、株価の変動や相続人の状況変化なども考慮し、複数のシナリオを想定して行うことで、より実効性の高い計画に繋がります。
計画策定納税資金計画の作成とスケジュール管理
試算した納税資金の総額を基に、「いつまでに」「誰が」「どの資産から」「どのようにして」資金を準備するのか、具体的な納税資金計画を作成します。
計画には、後述する資金調達方法ごとのメリット・デメリットを比較検討し、会社の運転資金や事業の継続性に影響を与えない最適な組み合わせを選択します。
5年後、3年後、1年後といった時間軸で具体的なアクションプランとスケジュールを管理することが成功の鍵です。
実行とモニタリング計画の実行と定期的な見直し
作成した納税資金計画は、一度作って終わりではありません。
計画に基づき、生前贈与や生命保険への加入などを実行に移します。
そして、少なくとも決算期ごと、あるいは経営者の健康状態や家族構成に変化があったタイミングで、計画の進捗状況を定期的に見直し、必要に応じて修正を加えます。
税制改正や事業環境の変化に柔軟に対応していくことが、計画倒れを防ぎます。

事業承継時の納税資金の調達方法
自己資金現預金や有価証券の活用
まず検討すべきは、会社および経営者個人が保有する現預金や換金性の高い有価証券を活用する方法です。
金利負担がなく最も手軽ですが、会社の運転資金や個人の生活資金を過度に圧迫しないよう、手元に残すべき資金とのバランスを慎重に考慮する必要があります。
借入金融機関からの融資
自己資金で不足する場合、金融機関からの融資も有効な手段です。
後継者が個人として融資を受け、納税資金に充てます。
融資を受けるためには、承継後の明確な事業計画を示し、会社の収益力と返済能力を金融機関に認めてもらう必要があります。
日頃から良好な関係を築いておくことが重要です。
生命保険生命保険の活用
生命保険は、納税資金対策として非常に有効な手段の一つです。
経営者を被保険者、会社を契約者・受取人とする保険に加入し、相続発生時に会社が受け取る死亡保険金を原資として、後継者に死亡退職金を支払います。
後継者はその資金で納税でき、また死亡退職金には相続税の非課税枠もあるため、節税と納税資金準備を同時に実現できます。
売却事業用資産や遊休資産の売却
事業に使用していない土地(遊休資産)や、収益性の低い賃貸物件などを売却して納税資金に充てる方法です。
ただし、不動産はすぐに希望価格で売却できるとは限らず、換金性に乏しいというデメリットがあります。
また、事業に必要な資産を売却すると、その後の経営に支障をきたす恐れがあるため、慎重な判断が求められます。
事業承継時の節税対策
贈与税の非課税枠の活用
年間110万円の暦年贈与の非課税枠を、後継者や他の親族に対して長期的に活用することで、相続財産を計画的に減らすことができます。
このほか、「教育資金の一括贈与」や「結婚・子育て資金の一括贈与」といった特例制度も有効な場合があります。
事業承継税制の活用
「法人版事業承継税制(特例措置)」は、一定の要件を満たすことで、後継者が承継した自社株にかかる贈与税や相続税の納税が100%猶予され、最終的には免除される可能性がある非常に強力な制度です。
ただし、適用要件が複雑で、承継後の雇用確保など事業継続義務もあるため、専門家と相談の上で慎重に検討する必要があります。
生命保険の活用
前述の通り、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という相続税の非課税枠があり、納税資金の確保と同時に相続税評価額の圧縮にも繋がります。
納税猶予制度の活用
どうしても現金での一括納付が困難な場合、分割で納付する「延納」や、不動産などで納付する「物納」という制度があります。
ただし、延納には利子税の負担があり、物納は許可要件が厳しいため、あくまで最終手段と考えるべきです。
まとめ
事業承継における納税資金計画は、税金の種類と計算方法、多様な資金調達方法、そして効果的な節税対策を、長期的な視点で総合的に考慮して策定する必要があります。
その計画は、会社の状況や経営者家族の想いによって、一つとして同じものはありません。
事業承継は思い立ったが吉日ではなく、準備に10年かかっても早すぎることはありません。
まずは自社の現状を正しく知ることから始め、事業承継に精通した税理士などの専門家のアドバイスを受けながら、綿密な計画を立て、円滑な事業承継を実現することが重要です。