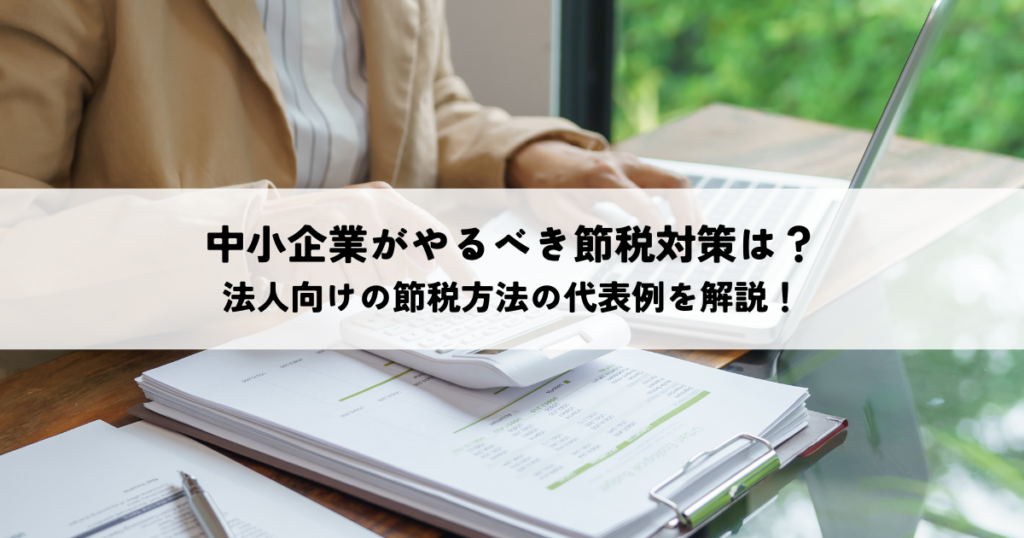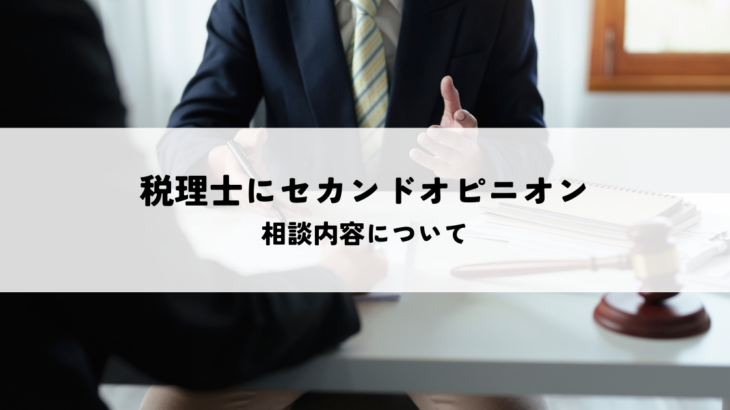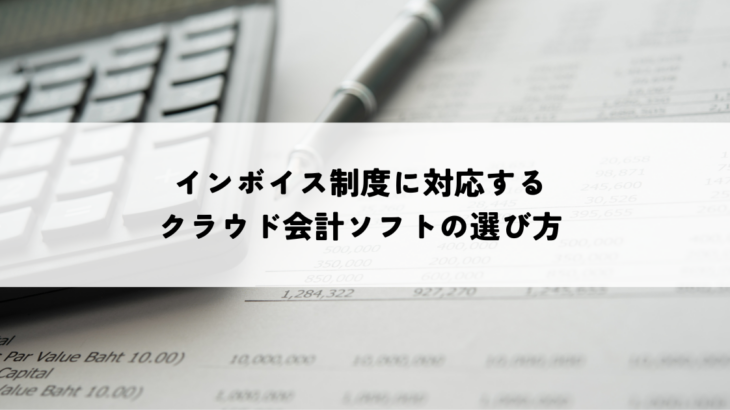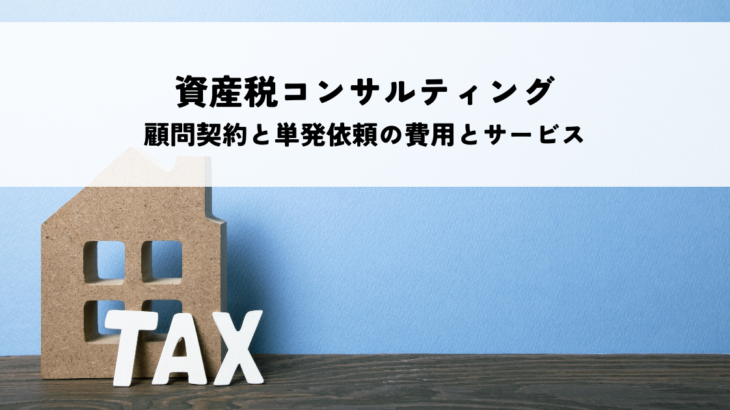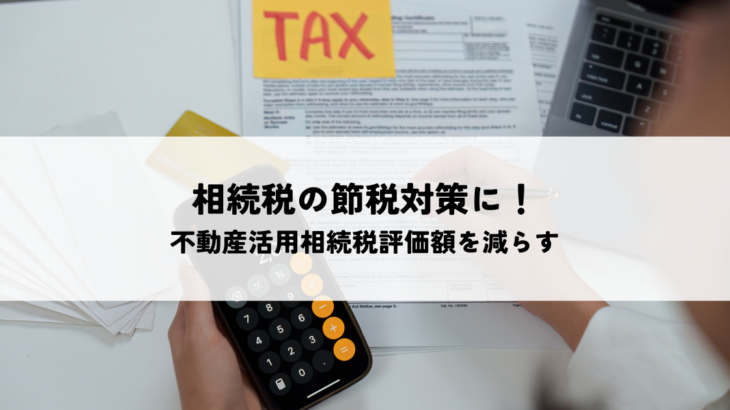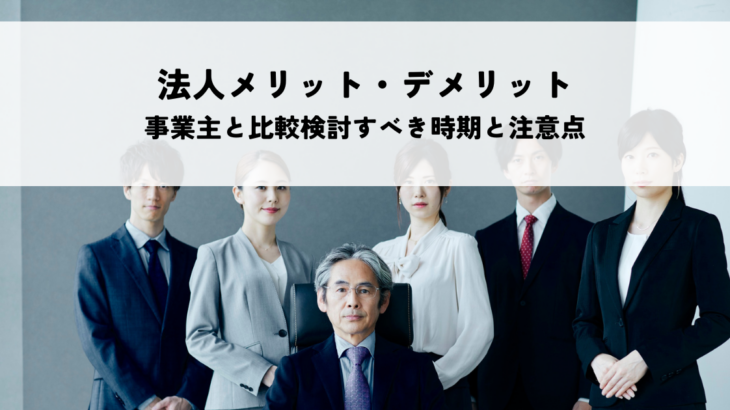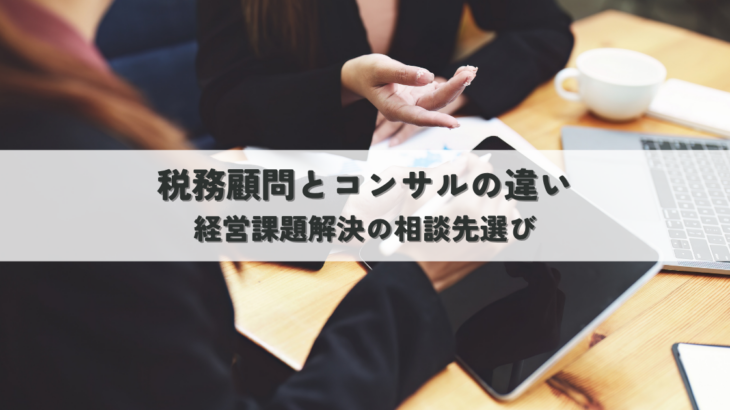企業の利益が順調に伸びていく一方で、法人税の負担の大きさに頭を悩ませることはないでしょうか。
有効な対策を講じなければ、手元に残るキャッシュは想定よりも少なくなってしまいます。
世の中には多様な節税対策が存在しますが、自社の状況に合わない方法を選んでしまっては本末転倒です。
そこで今回は、中小企業が取り組むべき節税の基本的な考え方と、自社に合った対策を選ぶための視点をご紹介します。
なぜ中小企業は節税対策に取り組むべきなのか
手元キャッシュを最大化するため
節税対策の最も直接的な目的は、支払う税金を抑え、会社が自由に使えるお金、つまり手元キャッシュを増やすことです。
キャッシュは企業の血液とも言える重要なものであり、潤沢なキャッシュは安定した経営基盤の証となります。
同じ利益額であっても、適切な節税対策を実行しているかどうかで、手元に残る金額には大きな差が生まれます。
新たな事業投資の原資を確保するため
節税によって確保したキャッシュは、守りのためだけではなく、未来への成長投資の原資となります。
例えば、新たな設備投資や優秀な人材の採用、新規事業の開発など、企業の競争力を高めるための前向きな活動に資金を振り向けることが可能になります。
これは、企業が持続的に成長していく上で不可欠な要素です。
企業の信用力を高めるため
節税対策に意識的に取り組むことは、無駄な支出を管理し、計画的な経営を行っている証左でもあります。
適切に利益をコントロールし、健全な財務体質を維持している企業は、金融機関からの評価も高まります。
融資を受ける際など、企業の信用力が問われる場面で有利に働くことが期待できるのです。

法人がすぐに検討できる代表的な節税対策
役員報酬の最適化による節税
法人の節税を考える上で、最も基本的かつ影響が大きいのが役員報酬の最適化です。
役員報酬は、原則として毎月決まった日に同額を支払う「定期同額給与」とすることで、その全額を損金(経費)として計上できます。
金額の決定は、利益操作を防ぐ目的から事業年度開始から3ヶ月以内に行う必要があり、一度決めると期中の変更はできません。
法人税の負担を減らすために役員報酬を高く設定すると、今度は個人の所得税や社会保険料の負担が増加するため、法人と個人のトータルでの税負担が最小になるバランスを見極めることが「最適化」の鍵となります。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)の活用
倒産防止共済は、本来は取引先の倒産に備えるための制度ですが、計画的な利益の繰り延べに活用できるため、多くの法人で利用されています。
支払った掛金は全額損金に算入でき、年間最大240万円、累計で800万円まで積み立てることが可能です。
また、加入後40ヶ月以上が経過すれば、解約時に掛金の全額が戻ってきます。
ただし、この解約手当金は全額が雑収入として課税対象になるため、役員の退職金の支払いなど、大きな費用が発生するタイミングに合わせて解約するといった「出口戦略」をセットで考えておくことが重要です。
出張日当・旅費規程の見直し
出張が多い法人であれば、旅費規程を整備して出張日当を支給する方法が有効です。
事前に全役員・従業員に適用される公平な規程を作成し、それに基づいて日当を支払うと、その全額が会社の経費となります。
受け取った側は、実費精算の必要がなく、一定の範囲内であれば所得税もかからないため、会社と個人の双方にメリットがあります。
日当の金額は、企業の規模や役職に応じて社会通念上、相当と認められる範囲で設定する必要があり、相場から大きく外れた高額な設定は税務署から否認されるリスクがあるため注意が必要です。
社宅制度の導入と活用
法人が物件を借り上げて役員や従業員に社宅として貸し出す制度も、節税と福利厚生を両立できる優れた対策です。
役員や従業員から法令で定められた計算方法に基づく「賃料相当額」の50%以上を家賃として受け取っていれば、会社が大家に支払う家賃との差額を損金として計上できます。
例えば、会社が15万円の家賃を支払い、従業員から5万円の家賃を受け取る場合、差額の10万円が会社の経費となります。
これにより従業員の実質的な手取りを増やし、企業の採用競争力を高める効果も期待できます。

自社に最適な法人向け節税対策の選び方
対策の基本は「利益の繰延」と「費用の活用」
節税対策は、大きく2つのタイプに分けられます。
1つは倒産防止共済のように、支払った時点では損金になるものの、将来的に利益として計上される「利益の繰延」。
もう1つは、広告宣伝費や修繕費のように、キャッシュを支出して費用を計上する「費用の活用」です。
どちらの性質を持つ対策なのかを理解することが、適切な選択の第一歩です。
視点1:年間の利益額で対策を選ぶ
自社の利益額に応じて、取るべき対策の規模は変わります。
利益がそれほど多くない状況で大規模な節税対策を行うと、赤字になったり資金繰りが悪化したりする可能性があります。
逆に、大きな利益が見込まれる期には、倒産防止共済への加入など、まとまった金額を損金にできる対策が有効な選択肢となります。
視点2:実施タイミングで対策を選ぶ
節税対策には、実施できるタイミングが限られているものがあります。
例えば、役員報酬の変更は期首から3ヶ月以内に行わなければなりません。
一方で、決算賞与の支給や、消耗品の購入、短期前払費用の特例活用などは、決算月でも対応が可能です。
年間計画の中で行うべきことと、決算間近で調整できることを区別して考えましょう。
視点3:手間とリスクで対策を選ぶ
対策によっては、導入に手間がかかるものや、税務上のリスクを伴うものもあります。
例えば、旅費規程や社宅制度の導入には、規程の作成や契約手続きといった準備が必要です。
また、あらゆる経費計上には、税務調査でその妥当性を問われる可能性があります。
手間やリスクを許容できる範囲を見極めることも重要な判断基準です。
節税対策で失敗しないために中小企業が注意すべきこと
過度な節税は資金繰りを悪化させる
節税を意識するあまり、必要性の低い保険に加入したり、不要な物品を購入したりすることは本末転倒です。
目先の税額を減らすためにキャッシュを過度に社外へ流出させてしまうと、肝心な場面で資金が不足する事態を招きかねません。
節税は、あくまで健全なキャッシュフローを維持する範囲内で行うべきです。
税務調査のリスクを常に意識する
行った節税対策が税務署に否認された場合、追徴課税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。
計上した費用については、それが事業に必要であったことを客観的に説明できる証拠(契約書や領収書、議事録など)を必ず保管しておきましょう。
常に「税務調査で質問されたらどう答えるか」という視点を持つことが重要です。
必ず税理士などの専門家に相談する
税法は非常に複雑であり、毎年のように改正が行われます。
インターネットの情報だけを頼りに自己判断で対策を進めるのは、大きなリスクを伴います。
顧問税理士などの専門家は、最新の税制に精通しているだけでなく、多くの企業の事例を見ています。
客観的な視点から自社に最適なアドバイスをもらうためにも、必ず専門家に相談しながら進めましょう。
まとめ
本記事では、中小企業が節税に取り組むべき理由から、具体的な対策、そして自社に合った方法を選ぶための視点までを解説しました。
節税対策には様々な種類がありますが、大切なのは自社の利益額や実施可能なタイミングを見極めることです。
また、過度な節税はかえって経営を圧迫するリスクも伴います。
この記事で紹介した注意点を踏まえ、税理士などの専門家とも相談しながら、計画的な節税対策を進めていきましょう。